家庭学習を習慣づけるコツは?小学校受験を成功させるために“今から”できること

保護者にとって、「わが子が学ぶ環境」はとても大切。小学校の6年間、あるいは中学までの9年間、高校までなら12年間という長い年月だからこそ、公立の小学校へ通うメリットよりも、私立の小学校へ通うことで得られるメリットに大きな魅力を感じる場合もあるでしょう。
小学校受験はお子様の成長を促すための、貴重な経験となる可能性を秘めているものです。
よりよい環境を求めて、より高い教育体制を求めて、そしてなによりお子様の成長の機会づくりとして、小学校受験への関心は昨今ますます高まりを見せています。
しかし、その一方では「初めての小学校受験、いったいなにから始めたら良いのかわからない」という声も多く寄せられます。
本記事では、小学校受験を成功させるための第一歩として「今からできること」をメインテーマに、日常生活で無理なく取り組める家庭学習や学びの習慣づくり、志望校選びのポイントについて解説してまいります。
小学校受験の成功に向け、まずは基本的な生活習慣の確立を目指しましょう

まず小学校受験の問題は、大きく次の下記の6科目に分類されます。
1、ペーパーテスト
2、行動観察
3、巧緻性テスト
4、運動テスト
5、口頭試験
6、面接試験
小学校受験を成功させるためには「知識量」が必要です。学校とは勉学を学ぶ場所なので、これは当然ですね。ただし小学校受験の場合、学力や知識量は合否を分ける重要な要素の一要素に過ぎません。
中学受験や高校受験、大学受験では学力が大きなウエイトを占めますが、小学校受験においては学力以外に「基本的な生活習慣の確立」もまた、評価の対象となります。
たとえばきちんと時間を守れるかどうか、身のまわりの整理整頓を心がけることができるかどうか、自分のことを自分でやることができるかどうかなどは「行動観察」として重要な要素となります。
このほか、あいさつの習慣や早寝早起き、食事マナー、朝食をしっかりと摂ることなども基本的な生活習慣の確立に欠かせない要素です。
これらは全て今日からでも始められる“学び”です。
小学校受験対策としてだけではなく、お子様の豊かな将来のためにも早い段階から取り組んでいけると良いですね。
学びの習慣づくりはどうする?小学校受験対策に役立つ家庭学習のコツ
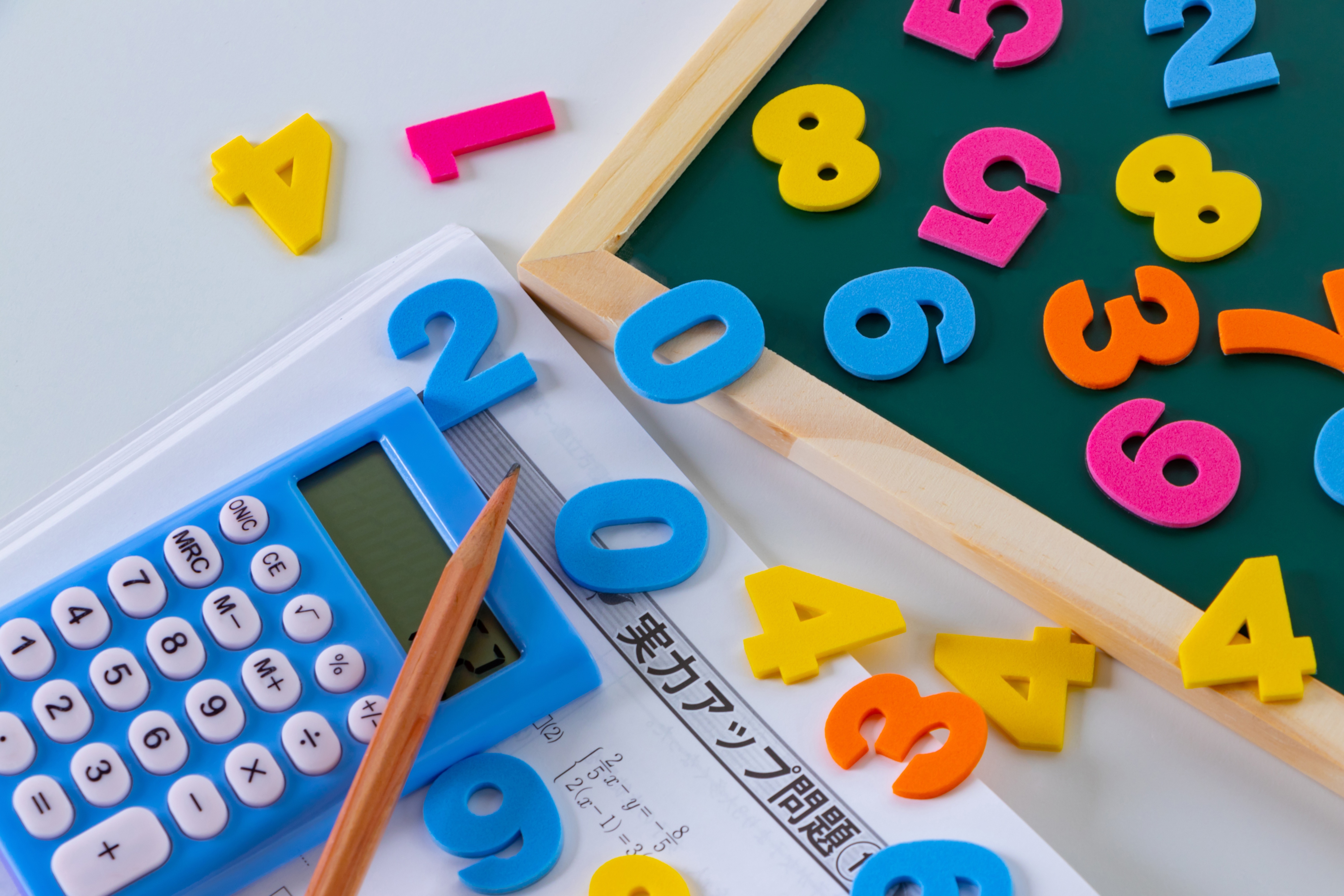
小学校受験対策の勉強法として、「プリント学習」は定番かつ有効な方法です。
しかし、勉強が習慣化していない状態で長時間机の前に座ることを求めたり、プリント学習を詰め込もうとするのは、お子様にとってストレスや負担になってしまう可能性もあります。
小学校受験の内容は、ペーパーテストだけでなく行動観察や運動、巧緻性など日常生活に関係するものや、親子関係に結びつく親子面接なども含まれます。そのため、日常生活の中に実践的かつ自然な学びを取り入れることが成長のカギとなります。「学びの習慣づくりをしよう」と意識するというよりは、学びを生活の一部にすることに目を向けると良いでしょう。小学校受験勉強の土台づくりとしては、まず「机に向かう習慣」や「本を読む習慣」あたりから身につけていきたいところです。
とはいえ、両親ともに会社員やフルタイムで仕事をしている場合、平日にわが子と向き合えるのは3〜4時間程度しかありません。食事やお風呂などにも時間をとられますから、受験勉強に使える時間はそう多くはないのです。そのため、隙間時間を上手に使うことが重要となります。短い時間でも毎日コツコツ積み上げることによって、大きな成果へとつながります。
学習時間の目安としては、最終的に1日90分以上確保できるようになるのが理想的ですが、本格的な受験対策を始める前のウォーミングアップとして、まずは勉強を生活の一部に組み込んでいくのが得策。それには隙間時間を上手に活用するのが良いでしょう。
隙間時間を上手に使うための方法について、朝・夕・晩にわけてそれぞれ例をあげてみたいと思います。
【朝】の隙間時間では「思考力」や「表現力」を伸ばす
朝は脳も体も活動しだしたばかりで、一番元気がある時間帯です。この時間帯は集中力も高い状態なので、学びの習慣づけをするにはぴったり。ただし朝はなにかと忙しくまとまった時間がとりにくいので、絵日記や簡単な内容のプリントなど、5〜10分くらいの短い時間で集中して行えるものを取り入れるのがおすすめです。
それが難しい場合は、朝食中にクイズ形式で一問一答をしたり、着替えの際にボタンの数を数えるのでも構いません。
通園時間を活用できるなら、この時間も有効に活用してみてください。しりとりで語彙力アップ、道端にあるものの名前クイズで知識量アップ、道路標識や看板で文字の勉強など、できることはたくさんあります。
「なぜ?」「どう思う?」などの質問を日常会話に織り交ぜることで、思考力や表現力を伸ばすことができます。このあたりの要素は面接対策にもつながります。
【夕】の隙間時間では「生活習慣」と「計算力」を伸ばす
幼稚園や保育園の帰り道、夕飯の材料のお買い物をしてから帰宅する場合、商品の値段を読み上げたり、食材の産地を確認したり、お釣りの計算を一緒に行うことで「数」や「比較」「順序」など考える頭を養えます。
また、お手伝いをしてもらうのも受験対策の勉強として役に立ちます。たとえば洗濯物に関連したお手伝いでは、洗濯物を畳む際に長方形や正方形など形の名前を学ぶことができます。お片付けでは、おもちゃを形や色ごとに分類して片付けたり、効率よく箱の中におもちゃを詰めたりすることで「図形の理解」や「空間把握認識力」、「計画性」について学ぶことができます。
【夜】の隙間時間では「好奇心」と「自発性」を伸ばす
お風呂の時間も学習タイムとして活用できます。おもちゃを使って浮力の実験や、お湯で落とせるクレヨンなどを使って数字や文字をつくる遊びを取り入れるのも良いでしょう。
お風呂ポスターを使ってなぞなぞ遊びをするのも良いですね。
寝る前の時間には、絵本を読んであげるのも効果的です。しっかりとお話を聞いて内容を理解する力が身につきますし、「語彙力」や「想像力」、「共感力」なども学ぶことができます。
また、お子様にとってのリラックスタイムとなるこの時間帯に「今日できたことを褒めてあげる」のも、お子様のやる気を維持しやすくなるのでおすすめです。自分自身の成長を一緒に振り返る時間は、親子の信頼関係を育むのにも役立ちます。
「家庭学習」というと堅苦しいイメージを持つかもしれませんが、実際には学びの楽しさを感じてもらうことと習慣化がカギとなります。
土日はどう過ごす?遊びも勉強も諦めなくてOK
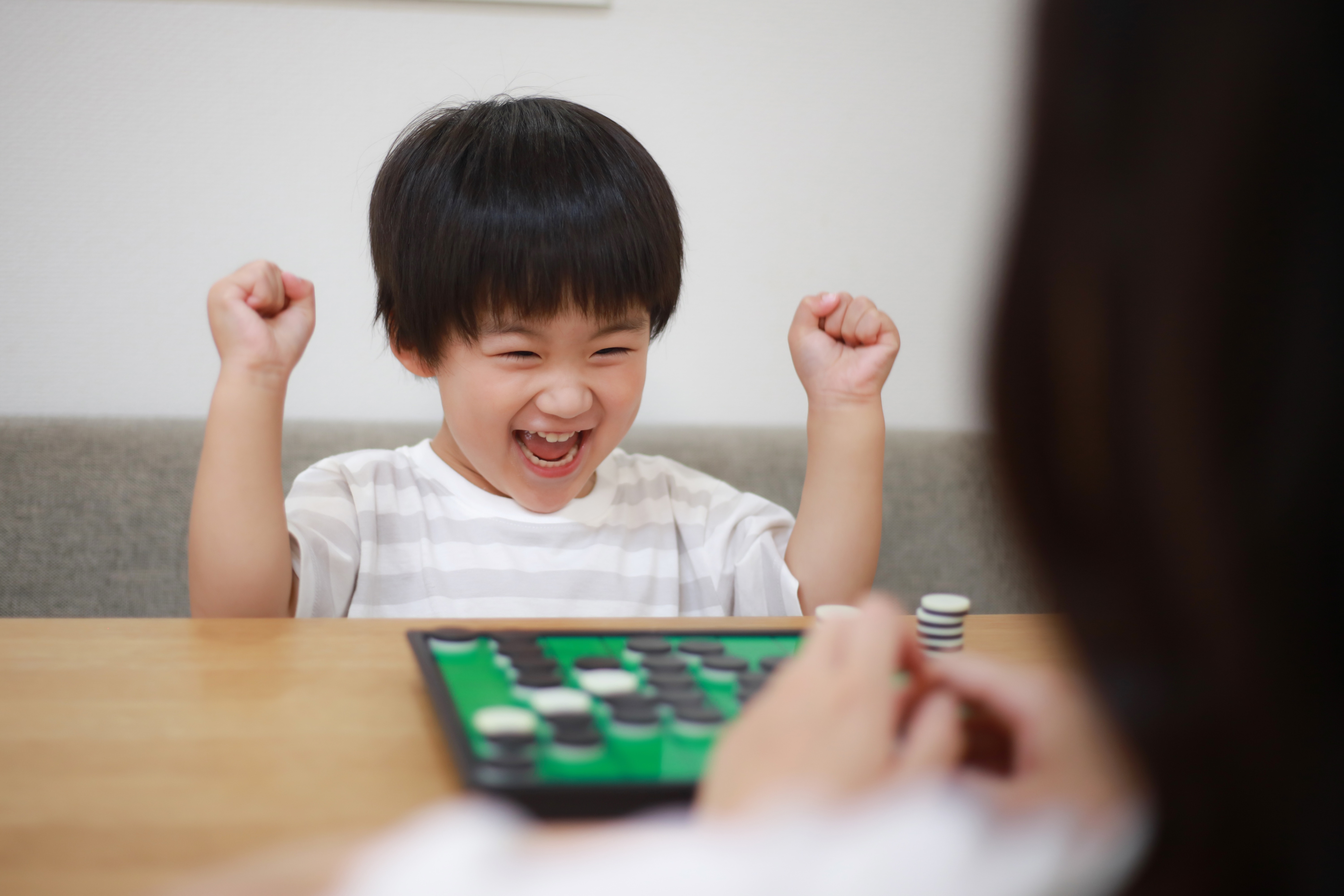
「平日はじゅうぶんな勉強時間を確保できないから、休日に詰め込んでしまいたい」と思う気持ちもよくわかります。しかし平日にも勉強をしているのに、土日まで勉強漬けの休日になってしまうと、お子様のストレスが大きく増えていってしまう可能性があります。お子様のやる気を削いでしまうのは本末転倒。なるべく避けなければなりません。
そのため、休日は「遊び」と「勉強」を混ぜてみることをおすすめします。たとえば、博物館や科学館で展示物を観て知識を深めたり、キャンプやハイキングを通して植物や昆虫の観察をしたり地図を読んでルートを探索するなど、遊びの中に勉強を組み込んでみてください。
また家族みんなでボードゲームにチャレンジし、戦略や思考力を伸ばすという方法もありますね。お子様とのコミュニケーションをしっかりと意識し、ストレスを軽減させつつ寄り添いながら受験の準備を進めてみてください。
何を意識して決める?志望校選びのポイントは

続いて、志望校を決定するにあたり意識したいことを3つお伝えします。
1、教育感や価値観をご夫婦で共有する
まずは、どのような環境で、どのように育ってほしいのかをご夫婦で話し合ってみてください。
「のびのびとした自由な環境で、興味関心を心のままに見つけてほしい」「規律を守り、しっかりとした見識を身につけてほしい」「自主性と創造性を身につけた優しい子になってほしい」など、将来どのように育っていってほしいのか、方針を決めていきましょう。
2、志望校の教育方針と家庭での価値観を見極める
志望校の教育理念や教育カリキュラムが、ご家庭の教育観や価値観に合っているかを確認するようにしましょう。学校のHPでの情報収集や、お知り合いの方にその小学校の情報をお持ちの方がいらっしゃれば話を聞いてみるのも良いでしょう。このほか、学校説明会やオープンスクールへの参加も効果的です。
3、通学距離は適切かどうかを判断する
お子様が無理のない範囲で通える距離の学校を選ぶことが大前提となります。小学校とご自宅の距離が遠すぎると日常生活への影響が出てしまう可能性があります。通学距離や通学時間が、学びの時間を圧迫することがないかという点もしっかりと検討したい重要なポイントです。
小学校選びは、「偏差値がちょうど良さそうだから」や「有名校だから」という理由を基準とするのではなく、「わが子に合っているかどうか」という基準で考えることが重要です。先入観にとらわれず、通える範囲にある小学校には広く足を運んでみると良いでしょう。
志望校が決まったら、具体的な対策を講じていきましょう

志望校決定後は、志望校の過去問を購入し、問題の分析や出題傾向を把握していきましょう。
その後、過去問に沿いながら、分野別・領域別の問題集を使って苦手分野を克服します。
お話、図形、絵の記憶、図形、推理思考、比較数量、常識の分野の中で、苦手な分野や出題傾向の高い分野を重点的に特訓していきましょう。
分野での特訓が終わったら、さらに細かく分けた単元別での問題集などを使用し、より細かく“苦手”にアプローチしていきます。年長の春頃までに基礎を固め、夏以降に応用問題に取り組むのが基本的な流れとなります。このあたりのフォローアップは、タブレット学習や通信教材、塾へ通うことで補うのも効果的です。
とはいえ、これはあくまでモデルケースでのお話となります。
さまざまな勉強法がありますが、「これが正解」というものはありません。お子様の性格や性質に合わせて、上手に組み合わせ、またアレンジをしながら行っていきましょう。




